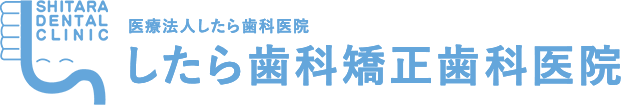卑弥呼の歯がいーぜ

今日、4月18日は「よい歯の日」です。 1993年(平成5年)に公益社団法人・日本歯科医師会が制定 。 歯科保健の啓発活動を目的としており、「よ(4)い(1)歯(8)」と読む語呂合わせからこの日に決定しました。
良い歯=「QOL(Quality of Life :人生の質・生活の質)を高めてくれる歯」でしっかりかんで健康に過ごしたいものです。
今回は日本咀嚼学会が提案する、噛む事の効用を咀嚼回数の多かった弥生時代の卑弥呼にかけて表した「ひみこのはがいーぜ」をご紹介します。
『ひ』……肥満防止
よく噛むと、満腹中枢が刺激され食べ過ぎ防止になります。
『み』……味覚の発達
食べ物本来の美味しさを感じる事が出来、味覚が発達します。
『こ』……言葉の発達
噛む事で、顔の筋肉が発達すると、言葉を正しく発音出来るようになり、顔の表情も豊かになります。
『の』……脳の発達
噛む事で、こめかみ付近がよく動き、脳への血流が良くなり、脳の活性化に役立ちます。
『は』……歯の病気を予防
歯の表面が磨かれ、唾液の分泌が良くなり、虫歯や歯周病の予防に繋がります。
『が』……ガンの予防
唾液の成分であるペルオキシダーゼには、食品中の発がん性を抑える働きがあるとされています。
『い』……胃腸の働きを促進
食品を噛み砕いてから飲み込む事で、胃腸への負担が軽くなり、胃腸の働きを正常に保ってくれます。
『ぜ』……全身の体力向上
噛み締める力を育てる事により、全身に力が入り、体力や運動神経の向上、集中力を養う事に繋がります。
昨今、健康食ブームで体に良い食材に注目が集まっているように思いますが、せっかくの体に良い食物もかまずに丸呑みしていては元も子もありませんよね。しっかりかんでしっかり吸収したいものです。