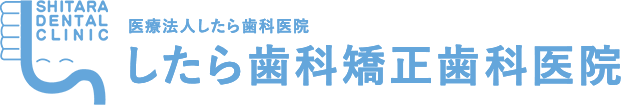ひな祭り

恒例のしたら歯科玄関ディスプレイに久々に飛び入り参加しました。院長からの「お雛様にして」と無茶ぶりに渋々作り始めたのですが、やりだしたら楽しい!ちょっとごてごてしすぎてしまいました (笑)
子どものころ母と一緒にお雛様の段飾りを飾った日を思い出したりして。三人官女の真ん中の多分女官頭が歯は黒いし、眉毛そっているしで怖かったんだよな~。母から「歯が黒いのは「お歯黒」っていうんだよ。歯を強くするために塗ったのよ」と聞いた覚えがあります。
このお歯黒、日本では古代から明治時代末期まで(場所によっては昭和の初めまでですって!)既婚女性に塗布するものとされ、引眉とともに既婚女性の「美しい」とされる顔だちを作るために必須だったようです。
お歯黒の塗布には気の遠くなるような手間と時間がかかったようです。
<染料の準備>
① お歯黒水(鉄漿水・かねみず)の作成
まず、ベースとなる「酸性の鉄溶液」を作ります
錆びた鉄くず、米のとぎ汁、お酒、お酢、麹、飴などを混ぜたものをお歯黒壺に入れ、数か月かけて発酵させます。いわゆる「酢酸第一鉄」溶液を作るのですが、すっごい臭いことは想像に難くありませんよね。腐った鉄溶液ですもん(汗)
② 五倍子粉(ふしこ)の準備
ウルシ科の白膠木という木にできる虫こぶ(五倍子・ふし)を乾燥させ粉末にします。渋みの成分である「タンニン酸」が大量に含まれている代物です
<歯への塗布>
① 加熱
使う分だけのお歯黒水を温めます。反応を促進させ色を濃くするためです
② 鉄溶液の塗布
お歯黒筆という鳥の羽根などで作られた筆や房楊枝を使って丁寧に塗布します
③ タンニンの塗布
お歯黒水が乾かないうちに五倍子粉を重ね塗りします
④ この作業を毎日~数日おきに繰り返し行う
酢酸第一鉄とタンニン酸を歯の上で非水溶性のタンニン酸第二鉄に化学変化させていたんですね!
すごいけど・・・考えるだけで気が遠くなりそうです(渋いし!くさいし!)
まぁ、確かに塚や墓から掘り起こされたお歯黒の痕跡が残る歯にはむし歯がほとんど見られないことがわかっていますから、効果は確実にあったようです。
はぁ~。現代に生まれてよかった~